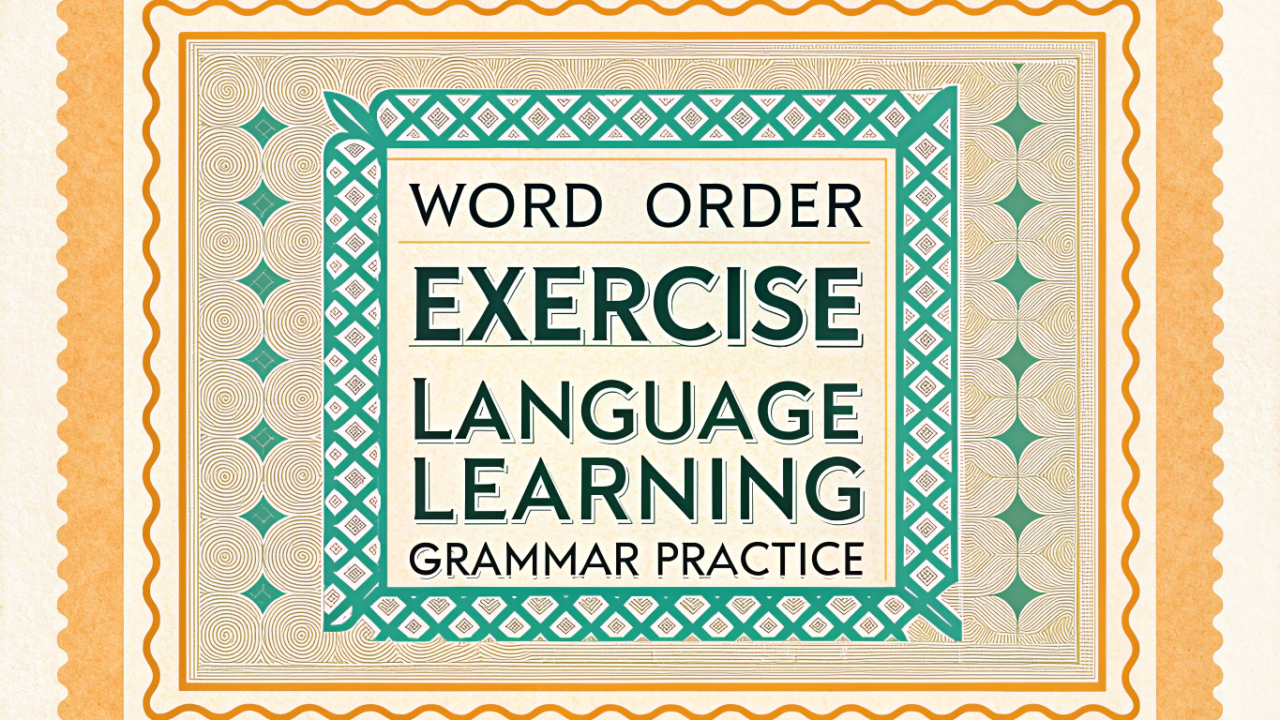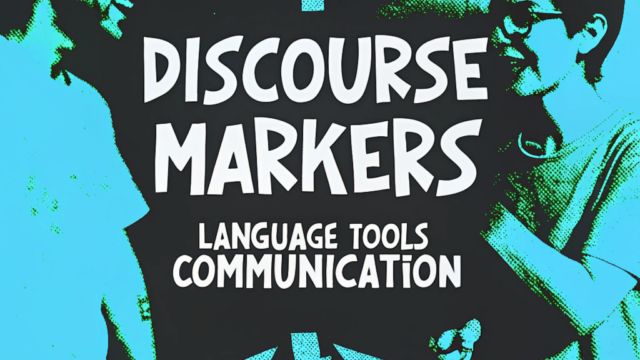目次
- 整序問題の本質と難関校で求められるポイント
- 5ステップ基本手順+α(難関大対応の追加視点)
- (1) 文の前後・周辺文脈の活用
- (2) 語句の品詞・形態を精密に仕分け
- (3) 熟語・構文・頻出パターンをブロック化
- (4) 文法骨格(文型)を組む+上級構文への注意点
- (5) 意味・文法・論理の最終チェック(音読含む)
- (+α) 難関大独特の視点・トラップ
- 難関大・上位校で狙われやすい複雑構文・表現
- 代表的な落とし穴+回避テクニック(上級編)
- 練習方法・復習方法(ハイレベル問題攻略のコツ)
- 高難易度例題(簡単な解説付き)
- Q&A:一歩先行くテクニカル・アドバイス
- まとめ:難関大合格を勝ち取るために
1. 整序問題の本質と難関校で求められるポイント
- 整序問題の根幹は「与えられた語句を正しく並べて英文を完成させる」ことですが、早慶・GMARCHレベルになると複数の節(従属節・挿入句)や抽象名詞を伴う分詞構文などが絡み、単純な「S + V + O + (修飾)」では収まらないケースが増えます。
- 難関大では、高度な熟語や特殊構文(倒置・強調構文・仮定法現在・分詞構文)がバラバラに配置され、見たことのない「隠れイディオム」やテクニカルな前置詞の使い分けなどが狙われがち。
- 文法力・熟語力・論理力・読解力を総合的に駆使しながら、スピーディーかつ正確に組み立てる必要があります。
2. 5ステップ基本手順+α(難関大対応の追加視点)
ここでは、基本的な5ステップに加え、難関大学だからこそ意識したい「+α」のポイントも示します。
(1) 文の前後・周辺文脈の活用
▼ 基本ルール
- 直前直後にある接続詞や時制、論理マーカー(e.g., however, therefore, moreover, nonetheless など)をチェック。
- 特に長文中の整序問題では、前の文の主語・時制・論理展開(因果、対比、例示など)を拾うことで、動詞の時制や代名詞の参照先、接続詞の種類などが自ずと絞り込めます。
▼ 難関大特有の注意点
- 特殊な挿入句(副詞や挿入的フレーズ)が頻出しやすい
- 例:“…, if any, …”(たとえあるにしても)、“…, if ever, …”(たとえあってもめったに)、“indeed,” “therefore,” など。
- 分詞構文や関係詞節が長めで、前後の主語がずれている場合もあるので、どの節がどこにかかるかを慎重に見る。
(2) 語句の品詞・形態を精密に仕分け
▼ 基本ルール
- 名詞・動詞・形容詞・副詞・前置詞に加え、動詞の形(原形、三単現、過去形、分詞形、to不定詞、動名詞)を精査。
- 同形異品詞に特に注意(e.g., “order,” “like,” “work,” “play,” “perform” など)。
▼ 難関大特有の注意点
- 複合形容詞や複合副詞(hard-to-please, long-forgotten, well-known, as well など)が選択肢に出る場合、どこに挿入するかがトラップに。
- 接続詞と前置詞が同形の場合:例 “since” (接:〜なので/前:〜以来)、 “while” (接:〜する一方で/名詞とセットで使うときは注意) などの区別。
- “to” の用法:不定詞 vs. 前置詞 vs. 副詞的強調 など。“But for” (〜がなければ) や “Except for” など紛らわしい前置詞との識別も狙われやすい。
(3) 熟語・構文・頻出パターンをブロック化
▼ 基本ルール
- 頻出熟語(take advantage of, make the most of, catch up with, etc.)や構文(It is … that, What … is …)を固まりとして識別。
▼ 難関大特有の注意点
- 仮定法現在(suggest / demand / insist / require / order … that S (should) V)
- should が省略されている場合が多い → 動詞の形に要注意。
- 強調構文+関係詞の組み合わせ
- 例:It was in 1985 that he founded the company which later became〜
- 分割されていると気づきにくいのでブロック化必須。
- 倒置(否定副詞、only+副詞、仮定法 if 省略形など)
- “Only when S V, 助動詞 S V …” / “Rarely do we find …” / “Had I known …” など。
- 分詞構文に付随する要素が長い場合
- “(Having been defeated in the last match of the season) , the team tried to …”など、一塊として捉えておかないと崩れる。
(4) 文法骨格(文型)を組む+上級構文への注意点
▼ 基本ルール
- S + V → O or C → 修飾句 の基本をまず押さえる。
- 接続詞や関係代名詞が加われば、節(S + V)が増える → 主節と従属節をしっかり区切る。
▼ 難関大特有の注意点
- 二重構文や複文:主節+(and / or / but)+従属節+挿入句…などで文が長文化。
- 名詞節を伴う動詞(e.g., think, believe, say, show, prove, realize, find)などが複数出てくるケース:
- “I believe (that he is right) and (that the plan should be revised).”
- that節が複数並ぶ場合、正しい位置関係を把握しないと大混乱。
- to不定詞が形容詞的/副詞的修飾になっている場合:
- “He had no chance to explain the reason why he left.”
- どこに置くかで意味が変わる → 選択肢を見比べるときに要注意。
(5) 意味・文法・論理の最終チェック(音読含む)
▼ 基本ルール
- 「声に出して読んだときに」ぎこちなさがないか。時制・主語動詞一致、意味の通り具合を確認。
- 論理的に不自然でないか:因果、対比、列挙の整合性。
▼ 難関大特有の注意点
- 論理マーカー(though, nevertheless, still, indeed, otherwise, likewise など)が複数出てくると、文意が複雑になる。
- 意味の自然さを優先すべき場合、細かい文法ルールだけでなく文脈の流れ(前後の論説・抽象度合い・筆者の結論など)も確認。
(+α) 難関大独特の視点・トラップ
- 同じ語形が複数ある場合の「省略」や「挿入」
- 関係代名詞の省略(that / which)の位置、所有格関係代名詞(whose)など。
- 時制一致が崩れやすいパーツ
- 過去完了 vs. 過去形、would vs. willなど。
- 比較構文が絡む
- “No sooner had S p.p. than S V …” / “Not until … did S V …” など、倒置を伴う比較・否定が同時に登場。
- 挿入句の置き場所による意味の変化
- 例:only, just, even, almost などの位置が変わると意味が変わる → 注意深く並べ替え。
3. 難関大・上位校で狙われやすい複雑構文・表現
以下に、早慶・上位私大でよく狙われる複雑構文や特殊表現を列挙します。整序問題で部分的に分割されていることが多いので、見た瞬間にピンとくるよう暗記&実践。
- 仮定法バリエーション
- 省略形:Had it not been for ~, Were it not for ~, Should you need ~
- 混合時制:If S had p.p., S would V (現在形や未来形) … など。
- 否定副詞+倒置
- Not only A but (also) B → 倒置を誘発するケースあり。
- Hardly/Scarcely ~ when/before S V, No sooner ~ than S V
- 名詞構文が長い
- “the possibility that S V ~,” “the reason why S V ~,” “the fact that S V ~” などの「名詞 + 関係節/that節」。
- 分詞構文の完了形・受動形・否定
- “Having been chosen as the leader, he decided to …”
- “Not having studied enough, she couldn’t pass …”
- 強調構文 + 関係節
- “It was not until 〜 that …,” “It is 〜 that …,” “It is because 〜 that …”
- 関係副詞(why, where, when, how)+複合関係詞(whoever, whatever, whichever)
- これらをうっかり関係代名詞として扱わないよう、周囲の品詞を吟味。
4. 代表的な落とし穴+回避テクニック(上級編)
- 重たい修飾語の位置取りミス
- 形容詞的修飾なのか副詞的修飾なのか混同し、主語と動詞が離れすぎて破綻する。
- → まず「S + V + (O/C)」を固め、修飾成分を入れる場所を慎重に選ぶ。
- 句動詞の一部が離れている
- 例:put ~ up with / look ~ forward to / catch ~ up with …
- 間に副詞や挿入句が挟まれている場合がある → 「本来の結びつき」を素早く見抜く。
- 複数の接続詞・副詞が近接
- while, if, since, because, though, as のように意味が似通うものを並べ、文意を混乱させる。
- → 前後の文脈と文法構造から最も適切な接続詞を選ぶ。
- 並置構文や同格構文
- “A, B, and C,” / “My father, a doctor working in London, …” / “We visited Paris, the capital of France, …”
- コンマの位置や名詞のあとにすぐ別の名詞がくるパターンに注意。
- “not … because ~” の論理ミス
- not A because B は「B だからといって A というわけではない」を意味 → 語順を少し変えただけで意味がひっくり返る。
5. 練習方法・復習方法(ハイレベル問題攻略のコツ)
- 問題演習は「量」+「質」
- 過去問・問題集で難度の高い整序問題を数多く解く。
- 解答後は「なぜその並びがベストなのか?」を論理的に説明できるまで調べる。
- 出会った構文・イディオムを「辞書/参考書」で深く調査
- 例:仮定法現在、特殊な倒置、強調構文などは構文自体を参考書で体系的に学ぶ。
- 錯乱させるための余計な要素(副詞、接続詞)を削ぎ落として骨格を見る訓練
- まずS+V+Oだけ拾って骨格のミニ文を作り、そこに必要な修飾語を1つずつ足す方法。
- 時間制限を意識した実戦練習
- 難関大では読解量も多い → 整序問題に割ける時間は限られる。
- 5ステップを素早く回せるよう、1問あたりの解答時間を短縮する練習。
- ミス分析
- 解けなかった問題・間違えた問題は必ず振り返り。
- 「どのステップでどんな判断ミスをしたか?」を振り返ると、同様のミスを予防できる。
6. 高難易度例題(簡単な解説付き)
以下、整序問題の例をいくつか示します。選択肢の一部を抜粋した形で表現していますので、並べ替え方針を考えてみてください。
■ Example 1
(1. that 2. he 3. if 4. would 5. had known 6. result 7. in such a 8. situation 9. avoided)
想定完成例:
(3) If (2) he (5) had known (1) that (8) situation (7) in such a (6) result (4) would (9) avoided.
→ 実はこれは倒置型「Had he known that ~」を誘導しようとするトラップ。「If」 があるように見せているが、if の省略形 (Had he known) への気づきが必要。最終的には、
Had he known that he would (have) avoided ~ の形で終わる可能性など、いろいろ混乱しやすい。
- ポイント:
- if / had known / would / avoided という並びが狙い。
- 仮定法過去完了(If he had known … he would have avoided …)か、倒置形 (Had he known … ) かをしっかり判断。
■ Example 2
(1. by chance 2. the manuscript 3. was discovered 4. centuries later 5. carefully hidden 6. in the basement)
完成例:
The manuscript, (5) carefully hidden (6) in the basement, (3) was discovered (1) by chance (4) centuries later.
- ポイント:
- “carefully hidden in the basement” は分詞構文というよりも過去分詞の形容詞句として manuscript を修飾。
- “by chance” “centuries later” は副詞句 → どこに置くかで読みやすさと意味を調整。
- カンマで挿入的に修飾句を入れている形に気づくかが勝負。
■ Example 3
(1. that 2. were 3. we do 4. completely 5. contradictory 6. the results)
完成例:
We found (6) the results (1) that (2) were (4) completely (5) contradictory.
- ポイント:
- the results that were completely contradictory → 関係代名詞節 (that were ~ contradictory) で the results を修飾。
- “completely contradictory” という形容詞+副詞のセットの位置が鍵。
※例題はあくまでイメージ。実際の入試問題はこれよりも長文の一部に整序が差し込まれるなど、さらに複雑になりがちです。
7. Q&A:一歩先行くテクニカル・アドバイス
Q1. 語数が多く、節がいくつもある。どうやって整理する?
- まずは節の数と種類を把握
- 接続詞(if, because, when…)ごとにS+Vの固まりがあるか?
- 関係詞節(関係代名詞/副詞)はどの名詞を修飾?
- 節ごとにミニ文を作ってから、それらをどう繋げるか検討する。
Q2. 仮定法現在や強調構文など、難関校特有のものが混ざるとパニックになる…
- まずは目印を覚える
- suggest, demand, order, insist → that節内で(should) 原形
- it is 〜 that … → 強調構文の王道
- 出来る限り「暗記+例文」で定番パターンを瞬間的に思い出せるよう訓練。
Q3. 選択肢の意味がどれもありそうで決めきれない…
- 文脈・論理関係を確認する。接続副詞(however, thereforeなど)による逆説・因果の有無で整合がとれるかどうか。
- 代名詞(he, she, they, it など)が何を指しているかを照合 → これにより文意が絞り込める。
Q4. 本番で時間が足りない…
- (1) 主語+動詞をまず一瞬で掴む → (2) 大きな構文(熟語・倒置・強調・仮定法)をブロック化 → (3) 修飾語の位置を微調整 → (4) 音読で確認。
- 演習段階でこの一連の流れを高速で回せるようにする。
8. まとめ:難関大合格を勝ち取るために
- 整序問題は英語力総合テスト:文法、熟語、構文、論理力のすべてが問われる。
- 5ステップ+αで確実に解き、難関大特有の倒置・仮定法現在・強調構文・分詞構文などをブロック化して捉える。
- 難問になると、前後の文脈や論理マーカーも絡めないと正解が導きにくい → 文章全体の流れを意識する。
- 訓練のコツ:
- 量をこなして構文暗記+品詞判断を高速化。
- 間違えた問題は必ず解説+背景文法を調べて根本的に克服。
- 時間制限を意識 → 実戦力アップ。
このプロセスを繰り返していけば、早稲田・慶應・GMARCHといった難関校のトリッキーな整序問題にも慌てず対処できるようになります。自分の弱点(倒置? 仮定法? 分詞構文? 接続詞?)を把握し、重点的に演習を重ねてぜひ高得点を狙ってください。
“整序問題を極める” = “英語力そのものを底上げできる” ということ。日頃の学習においても「この表現はどんな文型? 何が修飾されている?」と意識しながら英文を読む・書く癖をつけると、得点力が格段に上がります。
自信を持って練習を積めば、必ず難関大の英語整序問題で得点源を作れるようになります。 あとは演習あるのみ、頑張ってください!