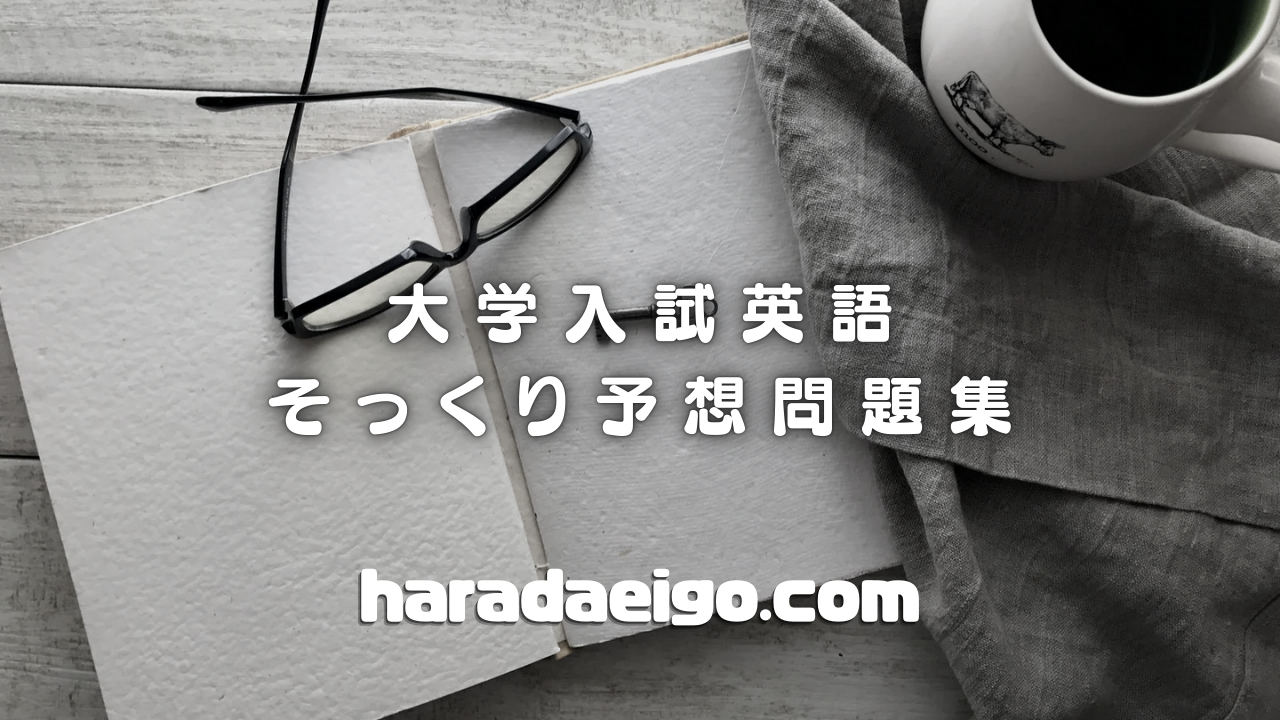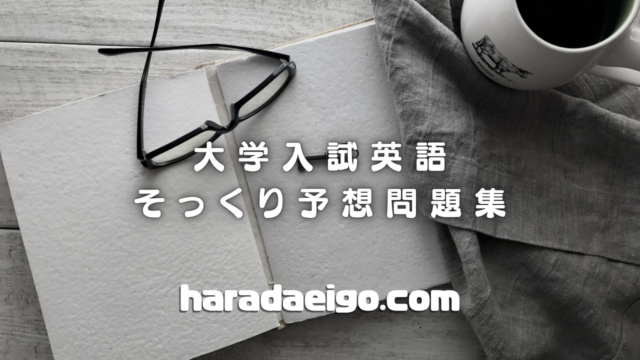〔本文〕
最近、オンライン学習やリモートワークの普及に伴い、デジタル機器を使って授業や仕事をする場面が増えている。私も先日、母校の小学校に招かれ、子どもたちがタブレット端末を使って調べ学習をしている様子を見学した。確かに、ネット検索のスピードは速く、画面上の豊富な資料から多様な知識を得られるのは魅力的だ。しかし一方で、児童の中には調べた情報をうまく咀嚼(そしゃく)しきれず、そのまま写しとるだけになっている様子も見られたのだ。先生が子どもたちに問いかけても、即座に答えが画面に出るので、真剣に考える前に「調べればいいや」と安易に流れてしまうように思えた。
私自身、便利なツールを否定するつもりはない。むしろ、限られた時間の中で効率的に情報を集められるのは大きなメリットだ。しかし、デジタル機器に頼りすぎてしまうと、実際に自分で試行錯誤する機会や、他者との対話を通じて理解を深める過程が損なわれる危険性があるのではないだろうか。情報を集める速さだけを追い求めるのではなく、得た知識を自分なりに解釈し、それを仲間と共有する中で新たな発想が生まれる――そうした深い学習体験こそが、これからの時代に本当に求められているのだと私は思う。
設問(英語)
Explain the author’s conclusion regarding digital tools in education and why she holds that view. Summarize the main points in about 80 words.
【模範解答】
The author acknowledges the usefulness of digital devices for rapid information gathering yet warns that overreliance on them may undermine genuine learning. She noticed children merely copying online data without fully digesting it, resulting in less critical thinking. Although speed can be beneficial, she believes true understanding emerges when knowledge is interpreted individually and shared collectively. Hence, her conclusion is that embracing digital tools must be balanced with hands-on exploration and deeper interaction to foster meaningful educational experiences.
(約80語)
【超絶詳しい 解答・解説・対策記事】
1. 読解&要約の基礎:本文の構造を5要素で捉える
お茶の水女子大学の英作文は、まず読解段階で本文の骨子を正確に掴むのが最重要です。以下の5要素を意識して本文を読みましょう。
- Situation(状況)
- どんな場面か:小学校で子どもたちがタブレットを使った学習。
- Problem / Conflict(問題・衝突)
- デジタル機器に頼りすぎると、思考力が育たず「調べて写すだけ」になる恐れ。
- Reaction(反応)
- 筆者はそれを見て、「便利だが危険もある」と感じた。
- Analysis(背景・理由)
- スピード重視で深い学びが損なわれる可能性。自分で試行錯誤・他者と共有する機会が減る。
- Conclusion / Message(結論・メッセージ)
- デジタルを否定はしないが、バランスが大事:深い学習体験を守る必要がある。
2. 設問の把握:何が問われている?
今回の英語設問:
Explain the author’s conclusion regarding digital tools in education and why she holds that view. Summarize the main points in about 80 words.
- 「筆者の結論は何か?」 → デジタル活用の利点は認めるが、依存しすぎが思考力・対話を削ぐ恐れがある → バランスが重要
- 「なぜそう考えるのか?」 → 子どもたちが写すだけになり、考える前に答えを見る現状を目撃 → 深い学習体験が失われるリスク
ここで重要なのは、「筆者が最も強調しているポイント」を漏れなく含めること。「便利さは認めつつも危惧を抱いている」「デジタルだけでなく、思考・対話・実践が必要」という2つの側面を押さえましょう。
3. 英作文の構成:70~80語でまとめる流れ
- 導入(1~2文)
- The author acknowledges… などで、まず筆者がデジタルツールを全面否定していない点を提示。
- 展開(2~3文)
- She noticed children merely copying… で、問題例を簡潔に述べる。
- その弊害(思考不足)を指摘。
- 結論(1~2文)
- Hence, her conclusion is… などで筆者の最終主張をまとめる。
- “バランスの重要性”が結論のキモ。
4. 模範解答の徹底解説
模範解答を分解して見ていきます。
- The author acknowledges the usefulness of digital devices for rapid information gathering yet warns that overreliance on them may undermine genuine learning.
- (訳) 筆者はデジタル機器が情報収集を素早く行える有用性を認めつつも、過度に依存すれば真の学習を損なう恐れがあると警告している。
- ポイント: acknowledges the usefulness → 「有用性を認める(否定ではない)」+ overreliance may undermine → 核心的な危惧を具体的に提示。
- She noticed children merely copying online data without fully digesting it, resulting in less critical thinking.
- (訳) 彼女は子どもたちがネット上の情報を十分に咀嚼せず、ただ写すだけになっていて批判的思考が低下する様子を目の当たりにした。
- ポイント: merely copying / without fully digesting → 問題点を要約。言い換えでコンパクトにまとまっている。
- Although speed can be beneficial, she believes true understanding emerges when knowledge is interpreted individually and shared collectively.
- (訳) スピードが有益であることは認めつつも、知識を自分なりに解釈し、仲間と共有することで本当の理解が生まれると筆者は考えている。
- ポイント: Although speed can be beneficial で譲歩→「筆者は一概にデジタルを否定してない」ニュアンス。
- interpreted individually and shared collectively → 本文中「自分なりに解釈」「仲間と共有」部分をうまく英訳。
- Hence, her conclusion is that embracing digital tools must be balanced with hands-on exploration and deeper interaction to foster meaningful educational experiences.
- (訳) それゆえ、デジタルツールを取り入れるにあたっては、実践的な探求やより深い交流とバランスをとりながらこそ、有意義な学習体験を育めると彼女は結論付けている。
- ポイント: Hence, her conclusion is that… で締め → 結論文として最適。
- “meaningful educational experiences” として、「深い学習体験」を英語らしくまとめている。
全体語数: 約80語。
5. スコアを上げるための具体テクニック
- 不要な副詞をそぎ落とす
- very, really, quite などは極力使わない → 語数節約&簡潔に。
- 1文1アイデア
- 長い一文に多要素を詰め込みすぎない → 要点が伝わりやすくなる。
- 接続表現を効果的に
- yet, although, hence など短く鮮明なコントラストを作る単語が有効。
- Furthermore, Nevertheless などの長い接続詞は字数を食うので注意。
- 筆者の立場を明示する
- She believes ~, She noticed ~, Her conclusion is ~, など、主体をはっきり書く。
- 文末で結論を強調
- 公式問題の傾向:最後に”The passage concludes that…”や”He/She concludes that…”を入れると内容が伝わりやすい。
6. 高得点を狙うための読解&書き方手順
- 読解
- 設問内容を先に確認 → 何を要約すべきか理解。
- 本文をざっと読み、問題点・結論・理由をメモ(Situation / Conflict / Conclusion など)。
- 要点整理
- 「筆者の結論は何か」「なぜそう思うのか」の2軸を明確に。
- 具体例(子どもの様子)やキーワード(スピード、深い学習、バランス)を拾う。
- 下書き
- 1文ずつ “導入→エピソード→筆者の分析→結論” の形で書く。
- 目安:4~5文、1文あたり15~20語程度 → 70~80語に収める。
- 推敲(削り&語数確認)
- 不要な形容詞・副詞・接続詞を削る。
- スペルミス、単複ミス、時制のズレをチェック。
- 最終確認
- 筆者の結論はしっかり含まれているか?
- 語数が問題指示と大きくずれていないか?
7. その他の注意点・アドバイス
- 主語を変えて読みやすく
- “The author” ばかり連呼せず、She, Her view, This perspective など多彩に。
- 中途半端に「自分の意見」を入れない
- 今回の設問は「筆者の結論とその根拠を要約せよ」と明示 → 自分の主張を長々書くと要約から逸脱し、失点リスク。
- 和文英訳的な単語直訳に注意
- 「大きなメリットがある」の直訳:There are big merits → 不自然。
- シンプルに It offers significant advantages など英語らしい表現に言い換え。
- 時間配分を意識
- 大学入試本番では読解&要約に時間を取りすぎないよう注意。2~3分で要点抽出 → 5~6分で作文 → 1分で見直しなど目安を決めておくと良い。
8. まとめ:お茶大英作文の必勝法
- (1) 読解段階が勝負
- 本文の論旨(何が問題で、筆者はどう結論づけているか)を的確に把握する力が8割。
- (2) 短い語数で的確にまとめる技術
- 70~80語では、冗長な表現はNG。端的かつ論理的にまとめる。
- (3) 結論文・理由付けを落とさない
- 「筆者は結局なにを主張しているのか」「なぜそう考えるのか」を必ず含める。
- (4) ミスを最小限に
- 時制・主語・単複・スペルなど基本の文法ミスを徹底的に避ける。
- 難しい表現に挑戦しすぎるより、正確でシンプルな英語が高評価につながる。
- (5) 過去問&模擬練習を繰り返す
- 時間を測りながら数多く書く→字数を調整→添削を受ける→ブラッシュアップするサイクル。
これらのポイントを踏まえて、70~80語の「短く、的確に、要点を押さえた英作文」を何度も練習すれば、お茶の水女子大学の自由英作文で高得点を狙うことができます。今回の予想問題はあくまで一例ですが、日頃から社会・教育・テクノロジーなど多様なトピックを意識し、要約力・英作文力を鍛えておくことが合格へのカギです。ぜひ、何度も手を動かして書いてみてください。応援しています!