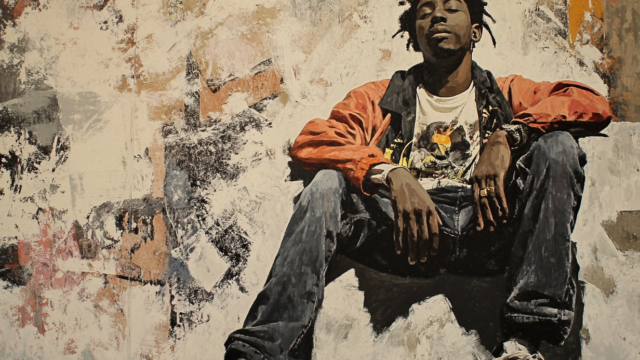今回は、2025年に知っておくべき最新のスラング100選を一挙にまとめました。SNS上の小粋な会話からリアルな雑談の場まで、「それってどういう意味?」を卒業して一歩リードするためのヒントがきっと見つかるはずです。ぜひこの一覧を参考に、新しい言葉のトレンドをキャッチアップしてみてください。
21. Simp(シンプ)
【意味】 特定の相手に過度に入れ込んで尽くす人。恋愛対象に見返りなく貢ぐ(媚びる)人を指す。日本語の「いい人止まり」「媚びへつらう人」に近い。
【例文】 “He bought her flowers again? What a simp.”(「また彼女に花買ったの?シンプだねぇ」)
【解説】 語源は“Simpleton”説や“Sucker Idolizing Mediocre Person”説など複数。もとは男性が女性に必要以上に尽くす様子への蔑称だったが、今では男女問わず「◯◯に入れ込みすぎな人」を冷やかすときに使われる。侮蔑的ニュアンスが強いため使用には注意が必要。
22. Stan(スタン)
【意味】 特定の有名人や作品に対し熱狂的ファンであること、またはそのようなファン本人を指す。日本語でいう「推しにガチ恋勢」「狂信的ファン」。
【例文】 “I’ve been a Taylor Swift stan since 2008.”(「2008年からテイラー・スウィフトのガチファンをやってます」)
【解説】 ラッパーのエミネムの楽曲『Stan』から来ており、インターネット上で「熱烈なファン」の意味になった。SNSでは「I stan ___」=「私は___の熱狂的ファンです」と動詞的にも使われる。度を越した愛を自嘲や揶揄する場合もある。
23. Sus(サス)
【意味】 「怪しい」「疑わしい」。suspicious(サスピシャス)の略で、何かの挙動に不信感を持ったときに使う。
【例文】 “Why are you coming home so late? Kinda sus.”(「なんでこんな遅く帰ってきたの?ちょっとサスいね」)
【解説】 2020年のオンラインゲーム『Among Us』から爆発的に広まった俗語。インポスターを指摘する際に「Red is sus.」などと言われたのがSNSミーム化し、日常会話でも「That’s sus.(それ怪しくない?)」と使われるようになった。
24. NPC(エヌ・ピー・シー)
【意味】 本来は「Non-Player Character(ゲーム内のモブキャラ)」だが、スラングでは「自分で考えずテンプレ通りの発言を繰り返す人」を揶揄する表現。
【例文】 “All his comments sound the same, like an NPC.”(「彼のコメント、どれも判で押したようでNPCみたい」)
【解説】 もともとゲーム用語だが、TikTok等で「NPCのようなライブ配信」が話題になり、「思考停止して周囲に流される人」を指して使われるように。相手を小馬鹿にするニュアンスがあり、冗談かネット批判で用いられる。
25. Sigma (male)(シグマ(メイル))
【意味】 社会的序列に属さず一匹狼的に成功している男性像を指す俗語。アルファ男(ボス的存在)でもベータ男(従順な存在)でもない「孤高の強者」。
【例文】 “He runs his own business and doesn’t care what others think – a total sigma male.”(「彼は自分の事業をやってて他人の目なんて気にしない、まさにシグマ男性」)
【解説】 インターネット掲示板やYouTubeで始まった男性性格分類ミーム。「Alpha male」とは別軸で群れを離れて独自路線を行く強者を「Sigma male」と称賛・ネタ化した。TikTokでは自己啓発やジョーク両面で盛り上がり、「Sigma grindset」という言葉も生まれた。
26. Chad(チャド)
【意味】 ステレオタイプなイケメン男子、自己主張が強くてモテる男性像を指す。文脈によっては皮肉や揶揄を含む。
【例文】 “He’s such a Chad, always acting like he’s better than everyone.”(「彼マジでチャドだね、いつも自分が一番みたいな態度してさ」)
【解説】 90年代頃から典型的リア充白人男性の名前としてジョークに使われ、ネットミーム「Chad vs. Virgin」でマッチョで能天気なモテ男の象徴となった。最近は「GigaChad」が人気だが、日常会話では「彼ってチャドっぽい」と皮肉混じりに使われることが多い。
27. Karen(カレン)
【意味】 サービス業の店員などに理不尽なクレームをつけたり特権的態度を取る中年女性を指す。日本語の「○○おばさん」に近いニュアンス。
【例文】 “The lady yelling at the cashier is a total Karen.”(「レジ係に怒鳴ってるあのおばさん、完全にカレンだね」)
【解説】 アメリカ発のミームで、白人中年女性に多い典型的クレーマー像を「カレン」と呼ぶ。語源は諸説あるが、2020年のマスク拒否事件等で「Karen」が広まり、「店長を呼べ!」などの行動が特徴的。男性版を「Ken」「Kevin」と呼ぶこともある。
28. OK boomer(オーケー・ブーマー)
【意味】 団塊世代(Boomer)の的外れな意見に対し、「はいはい(もう古いのよ)」と若者が一蹴するフレーズ。
【例文】
Older colleague: “You Gen Z are always on your phones.”
You: “OK boomer.”
(年上同僚:「最近の若者はいつもスマホばかりだ」 – あなた:「オーケー、ブーマー」)
【解説】 2019年頃にTikTok発で流行。世代間ギャップを痛感する場面で若者が年配者の説教を軽くあしらう際に使われる。辛辣だがミーム化しており、冗談として使われることも多い。
29. Based(ベイスト)
【意味】 「自分の信念に忠実でイケてる」「他人に迎合せずカッコいい」という肯定的な意味。ネット上では「よく言った!」「その意見支持する」と賛同の意味でも使われる。
【例文】 “He said what we were all thinking – based.”(「みんなが思ってたことを彼が言ってくれた――ベイストだね」)
【解説】 ラッパーのLil Bが提唱した「Based」(他人の評価を気にしない生き方)から派生。「超クール」「神ってる」のようなニュアンスで、「Based AF」「holy based」など強調形もある。Twitterなどで物議を醸す発言に“Based.”と返す文化も。対義語的に「cringe(イタい)」と返される場合も多い。
30. Cringe(クリンジ)
【意味】 「イタい」「見ていて恥ずかしい」。人や言動に対して鳥肌が立つ気恥ずかしさ・痛々しさを感じる際に使う。
【例文】 “His attempt at dancing was so cringe.”(「彼のダンス、見ててマジでイタかった」)
【解説】 元は動詞「すくむ」だが、ネットでは名詞・形容詞的に「クソ寒い」「痛い」ものを指す。「cringe compilation」という動画も人気。自虐で「I’m cringe, but I’m free」というミームもあり、日本語の「黒歴史」的なニュアンス。
31. Ratio(レシオ)
【意味】 SNS(主にTwitter)で、ある投稿に対する返信の方が多く支持を得ている状態(=元投稿が不評または否定されている状態)。
【例文】 “His tweet got ratioed hard by the replies.”(「彼のツイート、返信にレシオ食らってたね」)
【解説】 返信(リプライ)のいいね数が元投稿のいいね数を上回ると「レシオ負け」となる。SNS上では「Ratio」とだけ返信して相手の投稿への不支持を示す文化があり、多くのいいねがつくと投稿者よりそのリプライが支持されたことになる。
32. Ghosting(ゴースティング)
【意味】 (動詞: ghost)恋愛や友情で突然連絡を絶つこと。日本語の「音信不通にする」「フェードアウト」に近い。
【例文】 “We went on two dates and then he ghosted me.”(「2回デートした後、彼にゴーストされちゃった」)
【解説】 「ゴースト(幽霊)のように消える」が由来。恋愛相手から急に連絡が取れなくなる状況を指す言葉として2010年代に普及。SNSでも突然DMを無視して消える場合を「ghosting」と呼ぶ。
33. Catfish(キャットフィッシュ)
【意味】 ネット上で他人になりすます人、またはその行為。特に偽プロフィールや偽写真で恋愛相手を騙すケースを指す。
【例文】 “The girl I talked to turned out to be a catfish using someone else’s photos.”(「話してた子、他人の写真使ってるキャットフィッシュだったよ」)
【解説】 映画『キャットフィッシュ』(2010)から広まり、ネット恋愛詐欺を表す言葉として一般化。出会い系で別人の写真を使い「He got catfished.(騙された)」などと表現する。
34. Finsta(フィンスタ)
【意味】 “Fake Insta(gram)”の略で、本名やリア友には非公開のサブ垢(裏アカ)。友達だけに見せる本音投稿用インスタを指す。
【例文】 “I only post silly memes on my finsta.”(「私、フィンスタにはバカなミームしか投稿しないの」)
【解説】 Instagramユーザーの間で定着した用語。誰でも見られる本垢と異なり、仲間内だけに承認して日常の気軽な投稿をする場として使う。
35. Situationship(シチュエーションシップ)
【意味】 恋人未満・友達以上の曖昧な関係性。はっきり交際とは言えないけれど親密な「グレーゾーン」。
【例文】 “It’s not official, we’re in a situationship right now.”(「正式には付き合ってないけど、今はまぁシチュエーションシップだよ」)
【解説】 「situation」+「relationship」のかばん語。明確な交際に発展しないままデートや体の関係を続けている状態を指す。10〜20代でよく使われ、「I have a situationship with him」などと言われる。
36. Caught in 4K(コート・イン・フォーケー)
【意味】 「4K画質でバッチリ証拠を押さえられた」という意味。悪事や恥ずかしい行動が完全に動画で記録された状態を指す。
【例文】 “He tried to deny it, but there’s a video – he was caught in 4K.”(「彼は否定しようとしたけど動画に残ってるからね――フォーケーで押さえられてた」)
【解説】 高解像度で隠し通せない決定的証拠を握られた状況を面白おかしく言うミーム。SNSで誰かの浮気や悪ふざけが動画投稿され、「LOL you got caught in 4K」とコメントされる使い方が多い。
37. L(エル)
【意味】 「負け(Lose)」あるいは「敗者(Loser)」の頭文字から来ており、失敗や格下扱いを表す。誰かが恥をかいたり負けた時に「Take the L」などと言う。
【例文】 “I can’t believe I lost the game.” “Take the L, bro.”(「試合に負けたなんて…」「まあエルを受け入れなよ」)
【解説】 スポーツ・ゲーム界隈で勝敗を表すW/Lの略記法に由来。SNS上では「彼はこの件でL」など煽りに使われる。勝利にはW(Win)を使い「それWだね!」のように称賛を表す。
38. W(ダブリュー / ウィン)
【意味】 「勝利(Win)」を意味し、スラングでは「最高!」「よくやった!」を称える表現として単体で使われる。
【例文】 “You aced the exam? That’s a W!”(「試験満点?そりゃダブリューだわ!」)
【解説】 L(Lose)同様、勝敗の頭文字に由来。SNSで友達の投稿に “W” とコメントすると「すごい!」「よくやった!」に近い意味。別の言い方で “Dub” もあり、「We got the dub(勝ったぞ)」と使われる。
39. Yeet(イート)
【意味】 元は「(物を勢いよく)投げ捨てる」という動詞スラングだが、喜びや驚きを表す掛け声にもなっている。
【例文】 (throws phone onto couch) “Yeet!”(スマホをソファにポーンと投げながら「イェーット!」)
【解説】 2010年代半ばにVineのミームから広まり、投げる動作の掛け声として定着。その音感の面白さから、成功や歓喜を表す間投詞に転用され、TikTokでも「Yeet!」と字幕を付ける動画が人気。
40. Periodt(ピリオドゥ / ピリオド・ティー)
【意味】 「以上。終わり。これ以上言うことなし」と断言する強調表現。議論の締めや主張の結びに使う。
【例文】 “She deserves respect, periodt.”(「彼女は敬意を払われて然るべきなの。ピリオドゥ」)
【解説】 “Period.”(以上終わり)をさらに強調するために語尾の“T”を発音する形となった。ドラァグクイーンやヒップホップアーティストが広め、「~なの。Periodt!」とピシャリ言い切る感じで使われる。